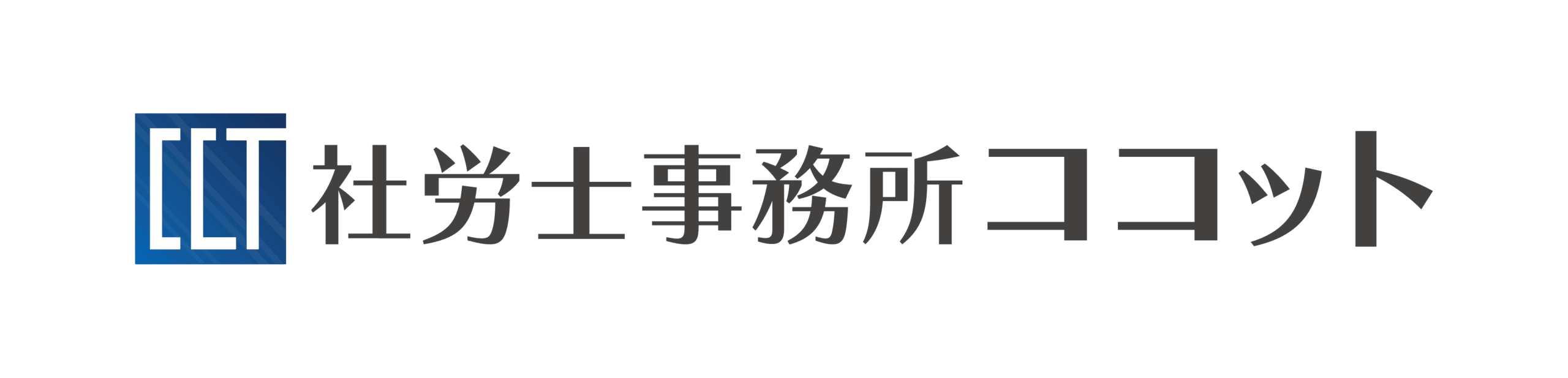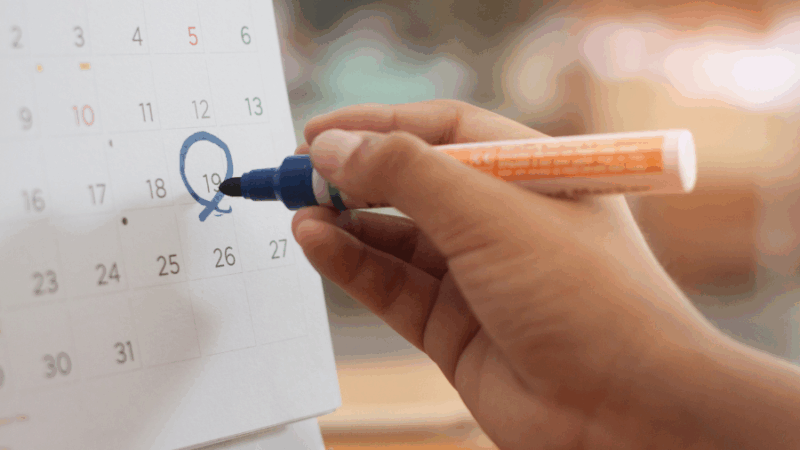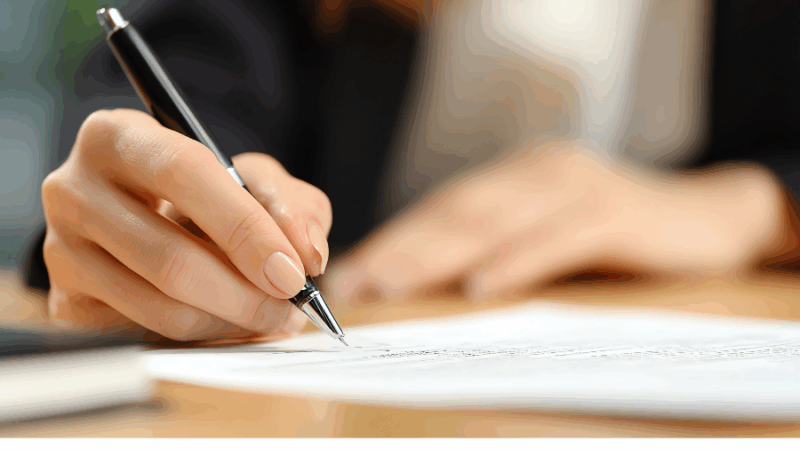令和8年度へ向けて。派遣労働者の待遇はどう変わる?
「同一労働同一賃金」の最新基準と、派遣元・派遣先の協力事項を解説
派遣労働者の公正な待遇確保は、労働者派遣法における最重要課題の一つです。
厚生労働省は、「同一労働同一賃金」の実現に向け、派遣元事業主に対し、待遇決定方法として【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】のいずれかを採用することを義務付けています(法第30条の3、法第30条の4)。
令和8年度に向けて、特に労使協定方式における一般賃金水準が大幅に引き上げられます。 派遣労働者の処遇向上と法令遵守のため、派遣元企業だけでなく、派遣先の企業の皆様にも連携の上、十分にご理解いただくことが不可欠です。
1. (派遣元・派遣先向け)令和8年度の「一般賃金水準」が大幅アップ
労使協定方式を採用する場合、派遣元は厚生労働省が毎年公表する「一般賃金水準」(派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金)を遵守する必要があります。
構造的な賃上げの流れを受け、令和8年度の基準額は前年度と比較して大きく引き上げられています。
A. 基本給・賞与等
基本給・賞与等については、業務別に厚生労働省が示す水準以上の額とし、さらに派遣労働者の能力や経験に応じた能力・経験調整指数を乗じる必要があります。
| 統計の種類 | 令和8年度水準(0年目・時給) | 前年度比の変更点 |
| 職業安定業務統計を活用した水準 | 1,289円/h | +3.3%(+41円) |
| 賃金構造基本統計調査を活用した水準 | 1,442円/h | +9.2%(+122円) |
B. 通勤手当・退職金
その他の待遇についても、以下の水準が求められます。
- 通勤手当: 派遣就業場所と居住地の通勤距離等に応じた「実費」を支払うか、手当額に上限を設ける場合は、厚生労働省が示す水準(令和8年度:1時間当たり79円)以上とする必要があります。
- 退職金: 一般基本給・賞与等に乗じる割合は、令和8年度は「5%」と定められています。
2. (派遣先向け)派遣料金に関する「配慮義務」の継続と強化
派遣労働者の公正な待遇確保には、派遣元が適正な賃金を支払えるよう、派遣先による派遣料金への十分な配慮が極めて重要です。
A. 派遣先が負う配慮義務とその範囲
労働者派遣法では、派遣先に対し、派遣元が公正な待遇を確保できるよう派遣料金について配慮する義務が課されています(法第26条第11項)。
この配慮義務は、派遣契約の締結時だけでなく、更新時などその後も継続して求められます。
B. 行政指導の対象となり得る行為
派遣先が配慮義務を尽くさなかった場合、行政指導の対象となり得るため注意が必要です。
- 派遣元から要請があるにもかかわらず、派遣料金の交渉に一切応じない場合。
- 派遣元が待遇決定方式に基づく賃金確保に必要な額を提示したにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合。
派遣元・派遣先においては、賃金水準の動向等を踏まえた十分な協議が必要です。
C. 「労務費の適切な転嫁」への対応
構造的な賃上げを実現するため、内閣官房および公正取引委員会の連名で策定された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った対応が求められています。
指針に記載された行動指針に沿わない行為(例:受注者からの要請の有無にかかわらず、明示的に協議することなく取引価格を長年据え置くこと)をすることにより公正な競争を阻害するおそれがある場合、公正取引委員会により独占禁止法および下請代金法に基づき厳正な対処が行われます。
3. 【派遣先均等・均衡方式】に必要な情報提供の義務
派遣先均等・均衡方式により待遇を決定する場合、派遣先は、派遣元の通常の労働者との間に「不合理な待遇差」がないように、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練など全ての待遇について決定する必要があります。
この方式を適切に実施するため、派遣先は以下の情報を派遣元に提供する義務があります。
- 情報提供のタイミング: 労働者派遣契約締結前、および当該情報が変更または更新される都度。
- 提供が必要な情報(例):
- ① 職務の内容や雇用形態。
- ② 比較対象労働者を選定した理由。
- ③ 比較対象労働者の待遇の内容(昇給、賞与などの有無を含む)。
- ④ 待遇のそれぞれの性質とその目的。
- ⑤ 待遇決定に当たって考慮した事項。
まとめ
令和8年度は、一般賃金水準の大幅な引き上げと、労務費の適切な転嫁に関するガイドラインの遵守が、派遣元・派遣先双方にとって重要なテーマとなります。
特に派遣元企業にとっては、派遣先クライアントとの事前の情報共有やコミュニケーションが必要となると考えられます。